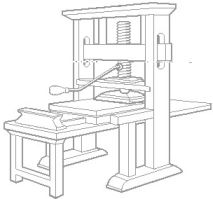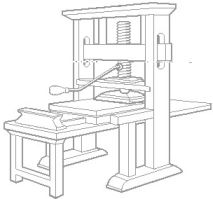感電
安全対策を設計の中に考慮しなければいけないのですが
まず人へ、装置へ、製品へ、環境への順に設計します。
機器・装置へは遮断器、検知器、ヒューズ、センサーなどで保護します。
人へは違う観点から同様の機器を使い安全を考えますが
感電の事故が起こると表のような事態になる事を理解していなければいけません。
全て人体を流れるとした場合を考えると
漏電ブレーカーは一般的には15〜30mAの製品を使用しますが
動作するときはとても危険な状態で動作するのが分かります。
溶接機用の漏電ブレーカーは100mAのものもありますが動作時には
生命の危険を伴う状態である事が分かります。
また漏電が感電に直結していなくても火災の原因など大きな災害に
つながる危険性があります。
といってノイズフィルターなどを使っている(機器の中に組み込まれていて
本人は使っていないと思っている事もある。)とある程度の漏電は起こりますので
動作電流を小さくしてしまうとメイン電源がすぐに切れてしまうように使えない
設計になってしまいます。
|
| 電流値 |
種 別 |
|
| (mA) |
感電の現象 |
| |
|
|
| 1〜2 |
最小感知電流 |
ピリッと感じる程度。 |
| 2〜8 |
苦痛電流 |
我慢はできるが苦痛を感じる。 |
| 8〜15 |
可随(かずい)電流 |
接触した電源から、自力で離れられる最大限度の電流、耐えられない程苦しい。 |
| 15〜50 |
不随(ふずい)電流 |
電源を感じながら自分で電源から離れられない電流、筋肉の収縮が激しい。 |
| 50〜150 |
心室細動電流 |
心臓の機能が失われ、たとえ電源から離れても数分以内で死亡する。 |
| |
|
|
|
|